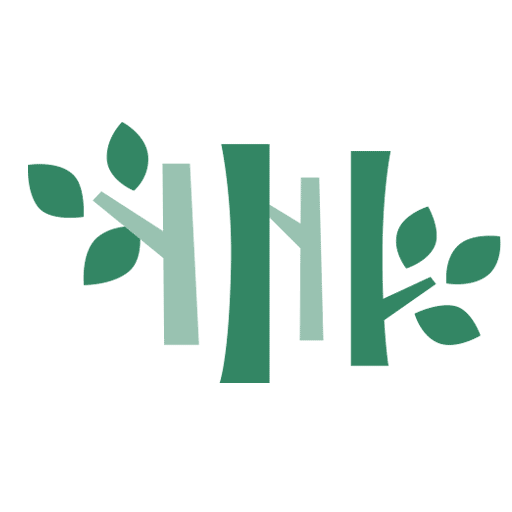まちかど学問のすゝめ 其の五

《木立のカフェ》はヴァーチャルでリアルな喫茶店。マスターの村井俊哉さん(京都大学精神医学教室教授)が京都市内の喫茶店をぶらっと訪れて、そこに集う人たちと「こころとからだ」「文化・社会」について語り合います。
今回は、カフェトークのお客さま、齋藤清二さんのお住まいの近く、堀川今出川tsubara café(ツバラカフェ)にお邪魔します。創業1803年の老舗「京菓匠鶴屋吉信」プロディ―スの茶房です。2019年オープン「はんなり」スペースでの“まちかど学問”となります!
暗がりでの捜し物
● 村井俊哉:1966年生まれ、京都大学医学研究科精神医学教室教授。最新の著書に『統合失調症』(岩波文庫, 2019年)がある
☆ 京都大学医学部附属病院 精神科神経科 公式サイト
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~psychiat/
● 齋藤清二:1951年生まれ、新潟大学医学部医学科卒。英国セントメリー病院医科大学研究員、富山医科薬科大学第3内科助教授、富山大学保健管理センター長/教授などを経て、2015年より立命館大学総合心理学部教授。最新の共
訳書に『ナラティブ・メディスンの原理と実践』(北大路書房, 2019年)がある。
☆ 木立の文庫webサイト《こころとからだの交差点》にて「リレーエッセイ」連載中!
https://kodachino.co.jp/dialogue/intersection-of-mind-body/mind-body-2/
アンチテーゼのハイジャック?


今日は齋藤清二さんとの “まちかど学問” 談義を愉しみにしています。齋藤さんは医師でありながら、医療のあり方そのものを捉え直す営みを続けてこられているので、精神医学、精神科医療にもからめて面白い話ができそうです。まずは齋藤さんといえば「ナラティブ」ということですね。

ナラティヴという視点はいまでこそさまざまな領域に浸透してきていますが、そもそもナラティブ・ベイスト・メディスン(NBM: narrative-based medicine)というムーブメントが出てきた背景を見ておきましょう。そこには、エビデンス・ベイスト・メディスン(EBM: evidence-based medicine)が世界中に広まって、それがちょっと広がり過ぎというか、行き過ぎている感じがあって、それに対するアンチテーゼという意味あいがあったんですね。もともとNBMを生み出したトリシャ・グリーンハル(Trisha Greenhalgh)などは、英国でいちばん売れているEBMの本を書いている人です。彼は、どうもEBMが変な方向へ行っているので、それをちょっと補正しなくてはならんということで、ナラティブを強調したというのがあります。ちなみにそのグリーンハルさんはいま、NBMも一段落したので、またEBMのほうに戻っています。

なるほど。僕もEBMが最初に出たときはすごく面白く感じました。特に精神医学は、実証的な姿勢にアンチな人が圧倒的に多かったので、EBMが登場した頃には、そういう状況に一石を投じて引っくり返してやろう! というような過激な面がありましたね。

そうです、そうです。

過激な人は、過激なうちは面白いんですけどね。それで定職を得たり、その道の権威となったり、というふうになってくると……。

実は、心理の世界でそのパロディみたいなものが起こっちゃっているわけです。一時期、医学におけるエビデンス・ベイストの思想みたいなのを心理の世界へ持ち込んで、しかも、それをかなり歪めた形で政治的に利用したというのがあります。

はい。

エビデンスの考え方を持ち込んだこと自体が悪いわけでもないんですけど、それがあまりにもひどい。アメリカではある程度それが修正されるのですが、日本ではぜんぜん修正されない。それを、私は「『エビデンスに基づく実践』のハイジャックとその救出」という論文を書いて、半分冗談で『こころの科学』という雑誌に載せたら、やっぱり一部の方が「我が意を得たり」ということで、「よく書いてくれました」というような反応がありました。でも、その人たちの考え方も僕とは違う。要するに僕は、エビデンスが気に食わないわけでは全然ない。そこは非常に複雑な思いなんですね。

今みたいなことを言っていると、EBMに反対派の人が応援してくれることもありますが、そういうことではないと、そうした意見にもまた反論したくなってしまいますね(笑)。

どちらかというと極端な人が多いので、その人がバーンと場を読まない発言をすると、炎上したりとか……。実際にTwitterを見ていると、今でも、そういう案件はとても多いです。僕から見ていると、どちらもべつに間違ったことを言っているわけではないんだけれども、完璧にボタンの掛け違いになっちゃって、議論は噛み合わない。

冷静な議論にならないんですね。

臨床心理学なんかでは、それなりのバランスをとって、多少いろいろ言う人はいても、それぞれの言い分を、できるだけ誰をも圧迫せずに出してもらって、「じゃ、この目の前のクライエントにどうするか」というあたりで落としどころをつかんでいくということは、ある程度できそうな気はしているんですよね。そこに、議論をする場と信頼関係のある安全な場がないとだめなんですけれども、具体的に「この人に対してどうするか」という議論については、大体それなりのところに行くんですね。

なるほど。

ひろがる暗い海と灯台

例えば「多元主義」という視点を村井さんは紹介されていますね。論理的な議論をしていると相容れないんだけれども、それは認めたうえで、どうやって実際にやることを調整していくか、みたいなところは大事なのではないでしょうか。

適材適所で最も優れた方法を使うべき、という「多元主義」は、実用的で優れた考えた方で私は共感しています。ただ、多元主義には一つ弱点があります。どういった時にどの方法が適材かを判断する際には、なんらかの基準が必要なわけですから、そうだとすると、多元的ではなくて、結局は一元的、ということになってしまうのです。だから多元「主義」というのは論理矛盾である、という見方もあるのです。
ただ、齋藤さんがおっしゃったようなプラクティカルという意味では、つまり、相容れない考え方もとりあえず両方置いておくというという意味では、多元主義はぴったりです。実は、先ほど言った論理矛盾のように見える点も私からすると矛盾ではないと思っています。でも、それを理屈っぽく説明しちゃうと、聞いている人はしんどくなるので、とりあえず多元主義とは「異なるものを仲良く同居させておいたらいいんだ」という考えだと説明するようにしています。

普通「見解の相違」としてしか認識されないので、意見が一致しなくても、相矛盾していてもいいんだというように合意に持ち込むというのは、ひとつの有効な方法だと思うんですね。そうでないと、そこの議論だけで疲れ果ててしまう。

人間の心について私たちが手にしている知識は極めてわずかなことで、いってみれば
「暗黒の海」のようなものです。先ほどのEBMですが、こうした暗黒の海のところどころにある灯台みたいなものだ。そういうイメージで考えればどうでしょうか。

はいはいはい。いい例えですね。

その暗黒の海を、俺はこういうふうな航海術で行くとか、俺はこれで行くとか言って、まあどっちも、間違いか合っているかわからないけれども、やっているうちに、「ああ、こっちが正しかった」とわかる。そういうふうに考えれば、何の不思議もない。
ところが、サイエンスとはもっとプレサイス(precise)に物事を予測できるもの、たとえば物理学モデルのようなものだと私たちがイメージしてしまうと、異なる航海術をとる人の間で船出する前から喧嘩になってしまう。たとえば、「〇〇精神療法」と「△△精神療法」のどちらが科学的に優れているか、などと堅苦しい言葉で言っていても仕方がない。それよりも、どういうふうに言葉かけをしたら相手の人はちょっと元気になってくれるだろうか、といったことの方が大切ですもんね。

うん、そうですよね。

そんなふうに試行錯誤でやっているわけです。そのときに、傾聴中心で行くのか、多少踏み込んでこちらも意見を述べるのか、どっちがいいんだと。こうしたことについてエビデンスをもとめて大規模な臨床試験に落としたところで、まあ出たとしても、「こういう研究の枠組みではこういう結果が出ましたよ」というだけのことですね。いまわれわれが航海しているか泳いでいる暗黒の「知識の海」みたいなイメージが、こうした結果を解釈する際のベースにあればと思います。

哲学というよりは、「一神教なのか多神論なのか」というような宗教的なメタファーのほうが近いような感じですね。ひとつの原理ですべてが終わっているのが一神教のイメージなんですけれども、いまの「知識の海」には、多神教的なイメージのほうが近いですよね。

多神教って、何か神さんがそこらじゅうにいるみたいですが、われわれが泳いでいる海というか、イメージというのは、その神様に滅多に出会えなくて……。たまに、お地蔵さんとかが助けてくれますが……またしばらくは、もう闇のなかで行かないとしゃあない。

だから臨床実践は、これはおそらく精神科でも身体科でも僕はあまり違わないように思うんです。よく、からだのことってスッキリわかっているけれども、こころは見えないからわからないんだという比喩をよく心理の人は使われるんです。
けれども、僕は全然そう思っていなくて、「からだ」だってぜんぜんわかっていない。不確実で、複雑で、ぐじゃぐじゃしていて、予測してもそれは当たるかどうかもわからない。海の中を泳いでいるときに、まあちょっと確からしいぞというのが、こうポッと……灯台のように……。

確実に治る病気もときどきありますけど、本当にときどきであって。

しかもそれは、どっちかというと、確実に治る病気って、ある意味、自然経過といいますか、待っていれば治るというほうが多いですよね。ある経過を邪魔しないでいれば。
ところが、そのときに何か複雑なことがたぶん起こっている。例えば炎症なんかそうですよね。最初にばーっと浸出液が出て、好中球が走ってきて、そのあとフィブリンが出てくる。実は複雑なことなんだけれども、怪我をしたところが、二日目には腫れるけれども、それがだんだん引いていって、一週間で治るというストーリーとして予測できるから、みんなびっくりしない。

そこで起こっているメカニズムを全部明らかにしようとすると、ものすごく大変なことなんだけれども、大雑把に言えば、ひとつの定型的なストーリーを利用しているからわれわれは医者をやっていけるので、それをしなかったら、もうドツボにはまるわけですよね。

そうです(笑)。

だから、すべて明らかにしないと医学はだめなんだとか、ちょっとでも不確実なことがあったらそれはだめなんだみたいなほうに行っちゃうと、むしろ、普通にやっていれば何とか泳ぎ着けるものが泳ぎ着けられなくなっちゃう。

そうですよね(笑)。

航海術のまえに

心理療法でもそうだと思います。冷静に見て行くと、だいたいどんな心理療法も優秀なセラピストが丁寧にやっていれば、半分ぐらいの人は確実に良くなる。確実というか、半分ぐらいは良くなると。でも、そのうちの三割ぐらいは実は、何もしなくても良くなるという人で(笑)、誰がどうやっても良くならない人というのがやっぱり二、三割いる。そういうところはコンセンサスとしてあって、あとは、その時その時に、どのぐらい状況に合わせた何かができるかみたいなことです。
暗い海を泳いでいる感覚で臨むと、こういうことが全体として見えるわけですよね。にもかかわらず、「認知行動療法以外は心理療法ではない」と言う人もいれば、「認知行動療法は、あんなのわざわざ人間がやることではない」みたいなことを言う人もいます。これは、どう考えても不毛でしょう。その辺はもう少し全体像を、あまり先鋭的にではなく、「こんなものなんだよ」というのを示してあげないと、いちばん困るのは、これから学ぼうとしている学生さんだろうと思うんですよね。

下手をすると、全人的に見るというのと、科学でやるというのが対立しちゃって、せっかく全人的にといっても、またそれと何かが対立するみたいなことで、きりがないんですね。なので、最初から「多元的なんですよ」というのはひとつの方便かもしれません。結構「しょせん暗い海だから」みたいな見方がしっくりくるんじゃないかなという思いがあります。

海のたとえで行くと、共通部分というのは、どの流派の「航海術」を使うとしても、「船というもの」はこうやらんと動かんよ、ということですよね。

(笑)そうそうそう。そう。

でも、ときどき、船ってこうやらんと進まんよねというのと「逆」のことをやっている人が、たまに、いはりますよね。

たまに、いはりますね。たぶんその「航海術」の流派の違いというものは、ある種の気象条件のときはある航海術でうまく乗り切れて、別の条件のときは別の流派の航海術が危機を乗り越える。でも、どの条件のときにどっちの流派で対応するかというところまでは正確にわかっていないので、たまたま今日の天候はこうだったので、日本流のチームがヨットのレースで勝ったけれども、今回の条件を日本の航海のあれにはもうちょっと合っていなかったかなというのはよく言うような感じなんですかね? それで、ところどころに目印になるような灯台みたいなものがあったりとかする。でも、そうは言っても、何回やっても圧倒的な差があってオーストラリアチームが勝つ。その航海術が世の中を席巻する。そういうことが医療でもあります。

これもメタファーですけれども、ソリの競技でワックスを間違えると、全然だめ、ものすごく実力のあるところでも、ワックスを塗り間違えると全然だめになっちゃうみたいなことってありますよね? たかがワックスなわけですね。だけど、やっぱりそういう小さいディテールが非常に結果を左右することはある。
けれども、そこばっかりに注目してしまえば、それでは、じゃあ、ソリの競技はワックスだけで成り立っているのかという話になっちゃうわけです(笑)。精神療法の技法ってそれみたいなものですよね。「確かに、それはそれで大事なんですが、まずそもそもやっぱりその基本技術があるか、という……」(笑)。ソリになってさえいないようなものに、いくらワックスを投じたってだめなので。

ちょっと研究の話に戻るんですけれども、その根本になっているところって、実証的なデザインがつくりにくいんですよね。基本になっているところが共通だからこそ、細かいところの実証デザインができるので。
ただ、どうしても医学全体の問題として「疾患があって、それを診断して、治療という介入を課す」というパラダイムがある。ところが、実際には、何かよくわからないけれども、「一緒にいたら治る」ということがあったりするわけですね。それって、非常に「デザイン」にしにくいですね。
なのにどうしても、やりやすいところのことが目立つし、評価される。いわゆる「夜の駐車場で落とし物をしたときに、街灯のあるところだけを捜す」ということですよね。

ああ、そうです。わかりやすい。

明るいところだけを捜しているということをやっているということは、自分ではわからないから、なんで暗いところを捜さないの? という話なんだけれども、しかし……明かりがないから捜せないんですね。
齋藤さんたちのされている分野もそうですし、僕らのところでもそうですけれども、精神医学は重症でない精神疾患といわれている気分障害とかはもう、「医療モデル」以外のモデルで社会が扱ったほうがトータルとしていいかもしれない、という考えさえ可能なわけです。
僕自身は医学の側の人間なので、医学モデルで扱うことを当然というふうに普段は語っているわけですが、そうした考え方に問題があるかないかということは、医学モデルのなかでやっている研究デザインのなかでは出てこないわけです。

はい、そのとおりなんです。ただ、自分にとっても耳に痛い話なので、あえてそういう発想をするためには、どうしても、ちょっと荒療治といいますか、外からの、あるいは、人類学的な視点とか、そういうものがないと、やっぱりそういう発想って、そもそも出てこないんですね。

ええ、そうですよね。

耳が痛いほうに耳を傾ける

「だから、「医療がむしろ病気をつくっているんじゃないか」という発想は、反精神医学とかいうことではなくて、常に考えていなければいけないことだと思っています。

僕は今でもすごく残念なのですが、反精神医学って、今日非常に評判が悪いんですね。昔は評判が良かったんですけど……。そういう時代に正統な精神医学の側にいて苦労した人たちは、反精神医学のことを黒歴史として全否定するわけです。

なるほど、なるほど。

ただ、そういう時代に苦労した先輩が反精神医学のことをそのように言うのを、下の世代の人が、単純に受け売りで、けなしている場面をみることがあるんです。やっぱり自分で一度ちゃんと考えたほうがいいですね。自分でそれなりに考えると、そう簡単に論破できない話って、結構あるんです。

はい、はい、はい、はい。本当に、そうですよね。

鵜呑みにしてやっているのはリスキーです。そういう、人の話を鵜呑みにしてずっとやってきた人って、人生のあるときに、例えば目論んでいたプロモーションがうまくいかなかったとか、家庭で辛いことがあったとか、何か自分の人生の危機に遭ったとき、突然、反医学とか、反精神医学とか、あるいはスピリチュアルやオカルトに唐突に向かうんですよ。
反精神医学やスピリチュアルが悪いということではなくて、唐突に大きくぶれてしまうことが何かおかしいと思うわけです。若いときに、ちゃんと自分自身で両方考えて、「こういうよい面もあるいけれどもこういう問題もある」といったことを考えた経験のある人は、のちに人生の危機にあったとしても、唐突に大きくぶれることはありません。

メタで考えている限りはぶれないですよね。なるほど、やっぱり免許を持っている者がそういうことを言い出すと、周りに対する害が大きいね。
私が今所属している学部ですと、人類学とか社会学との教員を採用していますし、そこである意味「反-心理学」風の話も、学生は聴く機会があります。教えている方々が「反-心理学」なわけではないのですが、考え方としては、いわゆる批判理論みたいなものがしっかり学べるので、まあある意味、そういうのはいいと思うんですね。

いいですね。耳が痛いものを排除しちゃうと、あとが逆に危ない。

純粋培養では、しっぺ返しが怖いですものね。

(2020年3月10日掲載)
■協力:tsubara café(ツバラカフェ) /取材:木立の文庫
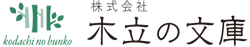


 磯野真穂(いその・まほ)
磯野真穂(いその・まほ)











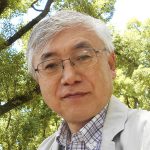

 岡田暁宜(おかだ・あきよし)
岡田暁宜(おかだ・あきよし)