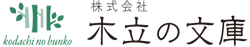非常識らしさの発想(1)
“ここ”に居るのは君と僕(2018年11月9日)
 藤中隆久(ふじなか・たかひさ)
藤中隆久(ふじなか・たかひさ)
1961年 京都市伏見区生まれ 格闘家として育つ
考えなおして1990年 京都教育大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)
九州に渡り1996年 九州大学大学院教育学研究科博士後期課程修了
南下して1999年から熊本大学教育学部 2015年から教授
推定5.8フィート 154ポンド
最近の大学入学試験は複雑で、いろんなタイプの試験が、年間に何度もある。僕も、試験監督やら、面接やら、会場警備やらを、訳もわからず言われるがままにやっている状態だ。それにしても、何でもやればいいってもんじゃないだろうと思う。適材適所という考えが大事だろう。僕が面接官をやることは「適材」を「適所」に配置しているとはいいがたい、と我ながら自信をもって断言できる。これが会場の警備ならば、僕もその適材性をいかんなく発揮して見せる自信はある。しかし、数々の自信はほとんど考慮されることもなく、毎年毎年、不適材な僕が、入試の面接という不適所な仕事を割り当てられているのだ。

「面接官に向いていない」という自信があるが、その自信はどこから来るのかといえば、僕は面接でいつも退屈するところにある。時には不快な気分にもなるからだ。受験生からすれば、面接官を退屈させようとか不快にさせようとかは、まったく思ってないはずだ。にもかかわらず僕は退屈になり不快感を感じているわけだから、面接官としての適性はないということだろう。
ほとんどの受験生は、僕の質問に対して、待ってました! とばかりに、まるでお芝居の台詞をしゃべるように、スラスラとよどみなく答える。しかし、こんな絵に描いた餅のような答えをよどみなくスラスラと返された日には、まるで、僕との対話を全身全霊で拒否されているような気分になる。こんなやりとりを、何十人もの、ほほを染めた三つ編みの高校生と繰り返さなければならないわけだから、退屈になるのは当たり前ではないだろうか。
この受験生たちは僕のことを「人格をもったひとりの人間」という風に想像してみたこともないのだろう。面接官が僕であれ、同僚Bであれ、同僚Cであれ、お芝居のように台詞をスラスラと答えるのだろう。どの試験官にでもお芝居のようにスラスラと同じ台詞を言うのなら、その場にいるのが僕である必然性はまったくない。いっそのこと、その場にボイスレコーダーでも置いて、それに向かって質問の答えを吹き込むよう指示してもいいのではないか、と思ってしまう。つまり、面接という場で僕は受験生から、人格をもったひとりの人間とはみられてはいなくて、ボイスレコーダーのような物とみられているのだ。人間を人間扱いせずに機械のように扱っている相手に対して、僕が不快を感じるのは、当たり前ではないだろうか。たとえ、相手が、ほほを染めた三つ編みの少女だったとしても。

僕は面接の場で人間同士の会話をして、もっと受験生とわかりあいたいのだ。ふたりのあいだで会話を弾ませ、会話のクオリティを高めたいと願っているのだ。会話が弾んだ結果として、思わず受験生の肩をたたきながら《もう、君、合格!》という失言をする覚悟さえも、僕にはあるのだ。そんな失言をしてしまっても、きっと同僚Bが《いまのは冗談だからね》ととりなしてくれるはずだから大丈夫だろう、と高をくくってもいる。そんな面接ならば、退屈したり不快になったりはしないだろうと思う。
お芝居のようによどみなくスラスラと答える面接戦略は、きっと、受験生が自分で考えてやっているわけではないだろう。受験生は高校や予備校で指導を受けて、訳もわからないままにやっているだけなのだろう。高校では面接のための想定問答集をつくり、想定問答どおりを面接の場でよどみなく演じるための訓練に余念がないのだろう。しかしながら、面接用の想定問答や訓練なんか、しないほうがいいと僕は思う。想定問答をつくったり訓練したりという戦略には、「真剣さが足らない」と感じられる。面接とは常に真剣勝負。だから、まったく準備などをせずに、想定問答もつくらずに、ぶっつけ本番で挑むべきなのだ。
受験生からすれば、「ぶっつけ本番で面接を受けたりすると、落とされるんじゃないか」との心配があるのかもしれない。「ぶっつけ本番で面接を受けると、言葉に詰まったり沈黙してしまったりしてしまうんじゃないか」という不安があるのかもしれない、あるいは「間違ったことや言ってはいけないことを言ってしまう」という不安があるのかもしれない。しかし、詰まったり、沈黙したりするということは、つまり、いまここで一生懸命考えて、自分のなかにある“まだ言葉になっていない思い”と必死に格闘しながら、それを言葉にする努力をいまここでやっている、ということなのだ。“いまを真剣に生きる姿”を受験生が目の前で見せているわけだから、僕などは、詰まるたびに、沈黙するたびに、いまを真剣に生きている三つ編み少女の面接点を5点アップしてあげるつもりだ。
~次回に続く~