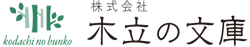[齋藤清二]
前回の投稿からずいぶん時間が経ってしまいました。その間の大きなできごとと言えば、もちろん昨年末に中国で始まり、一瞬のうちに全世界を巻き込んだCOVID-19(新型コロナウイルス肺炎)のパンデミックです。この新型感染症が私たちにとって、いったい何であったのかをある程度の距離感をもって語ることができるようになるには、今しばらく時間がかかるものと思われます。
そうはいっても、今回のCOVID-19が私たちにもたらしている影響は、このリレーエッセイのテーマである《こころとからだの交差点》にも、無関係であるとは言えません。今回の私のエッセイでは、不十分ではありますが、一部はこの問題にも触れながら考えていきたいと思います。
こころは身体との接点に浮かび上がる
何ものかである?
少し前に話題を戻すことになるのですが、第6回のエッセイにおいて、磯野先生は以下のように述べておられます。
これを読んだ時の正直な感想は、「え、え、オレって『身体との接点にあらわれる重要な何か』として “こころ” をとらえていたのか? ちっとも知らなかったぞ!」というものでした。
なるほど、対話というものはすごいものです。自分のライフワークといってもよいくらい長い時間、“こころとからだ” について考えたり論じたりしてきたのに、「他者の視点」が欠如していると、大事なことは何も見えないものなのですね。そうか、そうだったのか。自分が見ようとしている限り、見ようとしている自分は見えないのですね。それが見えるのは他者からだけ。しかし、自分が「見ようとしていることは何か」を表現して、他者に受け取ってもらえない限りない、それは「見られる」チャンスをもたないということになります。うーん、リレーエッセイ、やってみるもんだ。
つまり、私が “こころとからだ” の問題に惹きつけられるのは、私が “身体” をある程度、明確に意識しているからなのでしょう。“身体”を意識しなければ、身体でないものは生じてきません。おそらくこの「非身体」にいろいろと名前をつけようとするなかから、“こころ” という正体不明のものをめぐる「幻想」が生じてくるのかも知れません。なるほど磯野先生が、
とおっしゃっているのもむべなるかな、ということになります。
精神分析家と医師は違うのか?
ところで、磯野先生が「精神分析家としての岡田さん」と「医師としての齋藤さん」と、言葉をはっきりと分けているのは、私にとっては非常に興味深かったです。リレーエッセイとは言え、このような「現在進行形で関係をもっている相手との関係性に言及すること」は、(私の感覚では)とても勇気のいることです。うーん、このようなことが学べる以上、このリレーエッセイをやめるわけにはいきませんね。
実を言うと、岡田先生の第7回目のエッセイがこの上もなく精密かつ包括的であり、第5回の私のエッセイ、第6回の磯野先生のエッセイで提起された問題にほぼ全て回答してくださっていたので、正直のところ、「これはもう私がこれ以上、言葉を付け加える余地はないな」と思っていました。また、磯野先生の「ここには生徒も学生もいないのに、先生だけがいるのはおかしい」という指摘(これは、まさに「関係」についての言及なのですが)にいろいろ考えさせられるものがありました。しかし、このリレーエッセイという仮想の場には、間違いなく「学ぶ者」がいます。学ぶ者からみればそこには「教師」が存在する必要があります。よって、私は今後も磯野先生、岡田先生という呼称を使い続けることにします。
第6回目で磯野先生は二つの問いかけをして下さっています(適切な問いかけをして生徒に「自分の頭で」考えさせることは、「教師」の重要な役割であり必須の技術です。ただし、その質問は単なる評価のための質問であってはならず、生徒とともに教師も探求しつづけなくてはなりません。それが教育ということです)。その第一はこれです。
この問いに対して岡田先生は、前回のエッセイにおいて「精神分析家」の立場から明瞭に答えておられます。そうすると私は「医師」の立場から答えるべきなのでしょうか。しかし、これをそのまましようとするとおかしなことになります。岡田先生は「医師」であり「精神分析家」でもあります。私の理解では精神分析家は全て医師でなければならないということに今でもなっていると思います(岡田先生、もし私の理解が間違っていればご指摘ください)。このことに対してはいろいろな批判もあるだろうと思いますが、フロイトもユングも「医師」であったということは事実です。
医師が身体をあつかうということは
当たり前のことなのか?
しかし、磯野先生が話題に出してくださったユング心理学(分析心理学)では、分析家は医師でなければならないという条件はありません。私は医師ですが、人生のある時期にユング心理学の教育と個人的な訓練を受けたとはいえ、特に資格をもっているわけでもなく、専門家でもありません。なお、私が訓練を受けた三名の分析家は全て非医師でした。
私は日本のユング心理学のコミュニティにおいても「身体症状に苦しむクライエント」や「しばしば心身症と呼ばれる人たち」に焦点をあてて論じることが多かったのですが、思い返してみると、この苦しむ人たちは、身体医学の世界において「名前を与えられてこなかった」方々なのです。
多くのユング心理学の専門家は、このテーマについて肯定的な関心を示してくれました。しかし一方で、私自身の《心身》へのこだわりと彼らの興味関心には若干のずれがある、とも感じてきました。おそらくそれは、医師から出発してユング心理学の世界に入っていた私にとっては、「医師にとって身体を扱うことは当たり前のことであるが、実はそれがどういうことであるかは、自分ではわかっていない」ためだったのだろうと、今では思っています。
というわけで、上記の磯野先生の問いに対しては、私は医師として答えるということになります。
ここで磯野先生が「分析心理学=ユング心理学」のど真ん中とでも言うべき、〈アクテイブ・イマジネーション(能動的想像)〉を話題に取り上げてくださったことは、私にとっては僥倖でした。岡田先生も磯野先生も、〈能動的想像〉は専門家に指導してもらわなければ危険であるとの慎重な見解を述べておられます。しかし、(これを明言することにはかなり勇気のいることなのですが)私は実はそうは思っていません。
私の見解は、「私たちは誰でも能動的想像を日常的におこなっているし、それは多くの人にとって極めてありふれたことである。ただほとんどの人はそれに気づいていない」ということです。危険が生じるのは、能動的想像を「危険な目的」のために用いようとする時であり、かつ本人や指導者がその危険性に気づいていない時であると思われます。
もちろん、私は呪術の専門家ではなく、呪術については紙の上での知識しかもっていません。しかし、「呪術的なもの」という意味であれば、現代の私たちの生きている世界の少なく見積もっても半分くらいは、「呪術的な世界」であると言ってよいのではないでしょうか。特に今回のCOVID-19の問題のように、全く未知の恐怖に私たちのおそらく全員が晒されているような状況では、私たちは実に多くの「呪術的活動」を知ってか知らずかにかかわらずおこないますし、それを求めさえするように思われます。なにしろ「感染呪術」なんて言葉があるくらいですからね。しかし、この問題は論じると長くなりますので、機会があればあらためて述べたいと思います。
能動的想像と夢
さて、話を戻しますが、“こころとからだ”と〈能動的想像〉との関連について少し別の側面から述べたいと思います。
ご存知のとおり、深層心理学派は「意識と無意識の交流」という概念や実践を大切なものと考えます。〈能動的想像〉もそのひとつの特殊形態です。一方で、深層心理学派はクライエントの〈夢〉を大切なものとして扱います。〈夢〉が睡眠中の体験であることは、誰もが認めることと思いますが、その人が睡眠中にどのような体験をしたかについては、覚醒後に本人から聴くか、本人が記述したものを読むしかないので、その経験を他者が直接知る方法はありません。
精神分析は、近年ではどちらかと言えば、分析家と被分析者の関係性(特に転移-逆転移関係)を重要視し、夢分析(夢の解釈)を治療技法としてはあまり重要視していないように見えます。それに対してユング派は技法の中核に夢分析を置きます。夢を治療のなかでどのように扱うかは治療者によって異なりますが、ユング派の治療者は教育分析で自分自身の夢分析を徹底的に経験していますので、基本姿勢はおそらく一緒です。
〈夢〉は睡眠中の知覚体験であり、本質的に「対象無き知覚」ですが、〈能動的想像〉は覚醒中の体験です。〈能動的想像〉とは、一言で言えば、覚醒中に無意識のイメージが自律的に活動することを許す程度まで意識水準を低下させて、そこで生じる体験を詳細に記述していくことです。
このプロセス自体は、実は創作などの活動においては普通におこなわれていることで、例えば小説家は、作品の登場人物が作家のコントロールを離れて自由に行動したり発話したりすることを許します。
このようなことは何もプロの作家に限られたことではなく、近年の若者たちの間で頻繁におこなわれている二次創作などの同人誌活動なども、そのひとつだと思われます。夢小説と呼ばれるジャンルがサブカルチャーの世界に浸透していることも、このような現象を裏づけるのではないかと思います。
このような創作活動をしている時の、作家自身の身体はどう体験されているのでしょうか? 典型的な場合には、作者は自分の身体ごとその作品のイメージの世界に入り込んでいきます。この時の身体は、客観的に観察される身体ではなく、内側から体験される「生きている身体」の性質を帯びます。典型的な場合はこの両者は区別できないくらいに混じり合い、現実の身体にも大きな影響を与えるアクチュアルな体験が生じていると想像されます。
それでは〈夢〉の場合はどうかというと、私たちは〈夢〉において〈能動的想像〉と非常に類似した「意識と無意識の交流」を体験しています。しかし多くの場合、睡眠中は意識の力が覚醒中より低下しているために、その体験の意味を知り現実の生活に活かすためには、専門家の援けを必要とするとされています。しかし、ある種の例外的な夢においては、夢においても能動的想像と非常に類似した体験をすることが可能です。

オスラーの夢
ここで、現代臨床医学教育の父と呼ばれているウイリアム・オスラー(1849-1919)の話題に少しだけ触れたいと思います。
オスラーは「医学は科学に基礎をおくアートである」という言葉を遺したことで、現在も医師であれば誰でもが知っている存在で、おそらく、一人の医師が医学全てを網羅する知識と技術をもつことができた最後の時代の偉大な内科医でした。
オスラーがその晩年の約8年間にわたって、自身の夢の詳細な記録を遺していたことはあまり知られていません。オスラーはジークムント・フロイト(1856-1939)とほぼ同時代の人で、ごくわずかですがフロイトとの接点がありました。しかしオスラーの記録は、夢体験における状況・空間・感情などについての精密で詳細な記述の形式をとっており、フロイト理論による夢解釈の痕跡は全く見出すことができません。
そのシリーズのなかの夢のひとつとして、オスラーは「私自身の解剖」と題されたとても印象的な夢を記載しています。
この夢のなかではオスラーは、強い狭心症発作で前の晩に死亡しており、翌日、主治医であるギブソン医師による解剖がおこなわれ、オスラーは自分自身の遺体が解剖される場面に立ち会います。しかもオスラーは、幽霊としてその場にいるのではなく、身体をもった存在としてその場におり、同僚の医師たちもその状況に疑念をもっていません。
自分自身の身体が切り開かれ、全身の臓器がくまなく精査され、同僚の医師との間で冷静かつ詳細な議論が、夢のなかでなされます。その結果、オスラーの死因は若いころ知らずに感染した梅毒による大動脈病変が直接のきっかけとなった狭心症であったことが判明します。オスラーを含む医師たちが、大動脈の病変に病原体(スピロヘータ)がいるかどうかの顕微鏡検査をしようとするところで夢は終わります。
オスラーはこの睡眠中の体験をまるで実際の解剖に立ち会ったかのように詳細に描写し、記述していますが、そこには日時と時刻(4:30 a.m.)が記載されており、目覚めて直ちに書かれたまるでカルテのような記録であることは確実です。
この夢が深層心理学的にどのような意味をもつのかについては、複数の解釈が可能ですが、シンプルに考えると、この夢のなかでのオスラーの「ドッペルゲンガー」的な体験には、オスラーが到達した、身体に対する範例的な医師としての態度が表現されていると理解することができるかもしれません。
医師の関心は「何がこの身体の保有者の人生を終わらせたのか、その生理や病理はどのようなものであるのか、その歴史は何であったのか」といったことを、身体を精密に吟味し、描写し、それを記録に残すことを通じて探求することです。しかし、この夢のなかでの遺体としての自分も、それを観察・記録する自分も、ともに身体として体験されているにもかかわらず、それらの身体は実体ではありません。それは“こころ”の現われとしか言いようがないのです。
なお、オスラーはこの夢の記載の約2年後に、当時、欧州を襲っていたスペイン風邪に罹患し、併発した肺炎からの膿胸で死去しました。その遺体は、夢でおこなわれたと同じように主治医ギブソン医師によって解剖されました。梅毒性の病変は見いだされなかったと報告されています。
Long Covidの問題
最後に、磯野先生が提起された、「原因不明の身体の不調」が往々にして心因性と診断される時に生じる問題について、COVID-19と絡めて私からも問題提起したいと思います。
COVID-19は、高齢者や合併症をもった人における致死率は高いのですが、そうでない人の多くは無症候あるいは軽症で回復するので、社会にとってそれほどの脅威ではない、という言説がかなり広まっています。
しかし一方で、COVID-19に感染した人のうち、ウイルス学的検査では感染はもはや存在しないとされている人のうち少なくない割合の人が、3週間を超えて遷延する症状を呈することが明らかになってきました。この現象はLong Covidと呼ばれており、今後、COVID-19の医療上のケアにおいて大きな問題となる可能性があります。
Long Covidの約半数の人には、肺の線維化や中枢神経の器質的な異常などの、身体的異常が証明できます。しかし残りの半分の人には、明確な身体的な異常が証明できないにもかかわらず、呼吸困難感、全身倦怠感、不眠などの症状が継続し、QOLが長期的に障害されるようです。
これらの状態は「慢性疲労症候群」と類似しているという指摘がみられ、いわゆるコロナ鬱との関連も示唆されています。今後、Long Covidを訴える患者さんを身体的なものと心理的なものとに分けてラベルしようとすることは、絶対に避ける必要があると思います。これらの病態は連続しており、そもそも“こころとからだ”とは本来分けられないものであり、それを医師が無理にわけようとすることから問題が生じるということは、十分に考慮しておく必要があると思います。
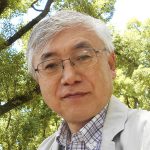 齋藤清二(さいとう・せいじ)
齋藤清二(さいとう・せいじ)
立命館大学総合心理学部教授
1951年生まれ、新潟大学医学部卒業、医学博士
富山大学保健管理センター長・教授、富山大学名誉教授を経て現職
こころの分野は、消化器内科学・心身医学・臨床心理学
からだの種目は、卓球