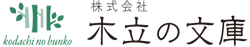日々これ想定外(その弐)
[藤中隆久]
いつの間にか経験者のように偉そうにシャドーボクシングを語っているけど、どうして僕がこんな事を詳しく語れるかと言うと、それは、僕が経験者だから。
その昔、僕はキックボクサーだった。プロのリングでも何戦か戦っている。なので、トレーニングをしているときの意識についても、よくわかる。シャドーボクシングのトレーニングをしているときの意識は、想定した対戦相手(シャドー)に向いていて、まちがっても「自己の内部」には向いていない。対人競技においては、相手に対して意識を向けることは当たり前で、相手に意識を向けながらトレーニングすることで、実戦に有効な技が身につく。

Tomorrow’s Joe, vol.14
現代武道の形稽古も、シャドーボクシングのトレーニングと同じく、目に見えない相手を想定して、その相手に向かって形が想定する攻防の動きをすることが、形稽古ということになるだろう。
ということは、常に「自己の内部」に意識を向けて、自己と対話をしながら稽古することこそが、強くなる唯一の方法であると考える古武道の形稽古は、現代武道からすれば「意味不明」で「非常識」とさえ考えられるのではないだろうか。
しかし、ここで考える非常識は、ホントに非常識なのだろうか?
生きるための「想定外」問答集
日本人にとっての常識が、キューバ人にとっては常識ではないかもしれないように、前提が変われば常識も変わる。
現代武道の前提とする戦いと、古武道の前提とする戦いは、かなり異なる。古武道の時代には、現代的なルールに従った形式の試合は無かったので、前提とする戦いは「ノールール」。だから、相手が何を仕掛けてくるのかはわからない、ということが大前提。
その後、現代武道が発展した大きな理由は、ルールを整備して試合ができる競技にしたこと。現代武道では、一試合で少なくとも5,6分は戦う。リングでは、1ラウンド3分で、3ラウンドとか5ラウンドとかを戦う。そして、勝っても負けても、さわやかに健闘をたたえ合って別れることが可能だ。

Tomorrow’s Joe, vol.9
かたや古武道では、失敗や負けは、すなわち死を意味する。だから、繰り出した技は必ず成功しなければならないし、戦いには必ず勝たねばならない。なので、5分も6分も戦ったりはしない。一瞬で勝負をつけるという戦い方を想定している。
このような違いがあれば、稽古法も異なってくるのは当然だろう。ノールールで、失敗が死につながる戦いでは、相手に一瞬のスキを見せることも許されず、また、相手に気配を悟られることも許されない。
したがって目指すべきは、黒田〔2000年〕が述べるような「軽く、柔らかく、速く、静かで浮いている。しかも美しく動きは消える」種類の動きとなる。あるいは、沖縄にルーツをもつ糸東流空手の宗家の摩文仁賢榮〔2001年〕が述べる「空手本来の形は居着いてはならない。これは素人目からすれば、ふにゃふにゃととらえどころのない動きに映るようです」というような動きこそが、よい動きということになる。
そのような動き方を身に着けるためには、自己の“いま-ここ”の内部の感覚を意識しながら、形稽古をおこなうことが大切になる。敵からの攻撃は、同じ状況ということはありえず、そういう意味では、常に「想定外」である。
「想定外」の攻撃を受けると、一瞬で、自己の内部は変わる。変わった自己の内部を一瞬で把握し、次の瞬間にもっとも効果的は反撃を繰り出すためには、意識を自己の内部に向けて、感覚を研ぎ澄ませて、その感覚に従ったもっとも合理的な動きを瞬時に選択する必要がある。形稽古は、その瞬時の感覚を養うためになされる。
関節を中心としたパワフルな技を繰り出す現代武道の動きは、成功することもあれば、失敗することもある。失敗が死を意味するノールールの状況では、そんな動きをするわけにはいかないのだ。
生きた自分と 生きた相手
前回の日記に綴った入試の面接での会話も、前提が違っている。
受験生は想定内の質問が来ることに微塵の疑いも持たない、という入試を舐めた態度をとっている。ところが面接官としては、受験生やそれを指導する高校の先生が想定している程度の質問など、したくない。どうせ、お芝居のセリフのように覚えてきたことをぺらぺらとまくし立てるだけの結果が目に見えているからだ。受験生の本音を聞くためには、その想定の上を行く質問がしたい。
面接官がそう考えているのならば、想定問答集を練習することは無意味となる。それよりも、どんな質問をされても、そこで生きた会話ができるようになっておくことが対策となるのではないだろうか。そんな人間になっておくためには、入試が近くなってから面接を想定して練習をしたりしてもダメで、常日頃からいろんなことを自分の頭で考えてみる練習をしておくべきだろう。そういう練習をしておけば、入試が近くなってから特に面接の練習をしたりする必要はない。
付け焼刃の練習よりも、日々の生き方が大事ということであり、これは決して“非常識”ではなく、むしろ普遍的な真理といってもいいくらいに常識的だと思われるが、いかがだろう。
となると、たとえばカウンセリングにおける会話も、クライエントに対して、良くなるためにいいアドバイスをするようなものではなく、“いま-ここ”で感じたことを述べてゆくというような会話であるべきではないだろうか。この前提を間違えると、ごくごく常識的な会話をクライエントと一緒にするという、非常識なカウンセリングをする羽目になってしまう。

Tomorrow’s Joe, vol.20
ところで、キューバでは、歌えるか、踊れるか、叩けるか(打楽器ができるか)が、男らしさの条件ということらしい。日本男児たるもの、歌ったり踊ったり楽器を演奏したりなどとチャラチャラするべきではないので、わが国ではそんな男がもてたりはしないが、キューバでは、これができれば、女性にモテモテらしい。
真面目人間ゆえに、わが国ではイマイチもてない私だが、これで、けっこう歌えるし踊れるし叩けるので、いずれは、キューバに移住しようか? などと考えているところである。どうせ、私の人生は、ずっと、南下しぱなっしなのである。
 藤中隆久(ふじなか・たかひさ)
藤中隆久(ふじなか・たかひさ)
1961年 京都市伏見区生まれ 格闘家として育つ
いろいろあって1990年 京都教育大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)
西にシフトして1996年 九州大学大学院教育学研究科博士後期課程修了
南に下りて1999年から 熊本大学教育学部 2015年から教授
6フィート2インチ
現在200ポンド:当時170ポンド